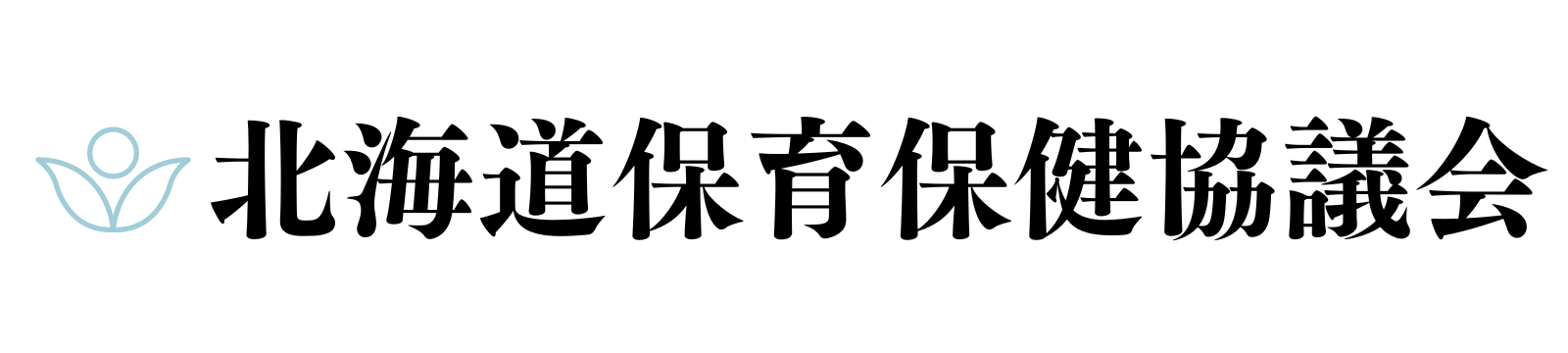北海道保育保健協議会について
会長あいさつ

北海道保育保健協議会の古田です。
日本保育保健協議会の北海道支部的な位置づけで日頃の活動を続けております。会員は、医師(主に小児科医)、保育園(保育士・看護師・栄養士)、教育機関(保育・保健分野)関係者などで構成され、調査・研究活動を通じて、主に保育・健康に関する情報を会員に提供しています。
発足当時は、保育園だけだったのですが、今は認定こども園(2006年)、小規模保育授業所(2012年)など、多岐に渡ります。
規模も配置されるスタッフの数も異なり、現場の課題はそれぞれに違います。
会の性質上、主に子どもたちの健康の問題取り上げてきました。
当初は、心臓・腎臓・喘息など日常生活の活動に支障がある疾患について、子どもたちの生活の制限・健康指導について情報発信していました。2000年以降になると医療の進歩によってかなりの制約が取り除かれています。
一方、食物アレルギーについては、「原因食物を極力回避する」治療から、「少量ずつ摂取する」ことにより早期離脱を図る治療が始まり、保育園でも、食事の管理やアナフィラキシー症状に対応することが求められるようになりました。
乳児期のワクチンが増えて、小児科・耳鼻科の診療ではかなりの細菌感染症が減ったのですが、「かぜ」の類(たぐい)のウイルス感染は変わりません。検査の普及によって、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルスなど名前はつくようになりましたが、対応は変わりません。うがい・手洗いとよく子どもたちが「触れる」ところの保清、消毒になります。
ところが、2019年末に始まった新型コロナウイルス感染症からその意識は一段と高まりました。今後も注目していかなくてはなりません。
当会もDX化には程遠いのですが、遅ればせながらホームページを作成しました。
ペーパーレス、郵送料の節約、刊行物の発行以外にも情報発信できればと考えています。
また、少子化が進んで、保育施設でも定員割れが生じていると思いますが、小児科医療も同様で、道内も都市部以外の地域では、病院小児科の規模縮小・廃止、小児科開業医の閉院(継承なし、新規開業なし)も相次ぎ、組織の改編も必要になってきました。
今後も当会の活動に会員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
北海道保育保健協議会
会長 古田博文